
毎日、コーヒーを飲めることはとても幸運なこと。
"AllSync.jp"へようこそ。Sync.(@AllSync.jp)です!
ワークショップを終えて、一番感じたこと。見たり聞いたりしたことしかない農園の環境を、想像で置き換えて得た感想ではあります。
サステナビリティ(持続可能性)やトレーサビリティ(追跡可能性)というキーワード、詳しい方や何となく知っている人も多いと思います。食べ物や着る物から生活に関すること全てにおいて、快適で便利であることが当たり前のこの世界で、大切な概念として提起されています。
世界全体が持つ問題は何となくニュースで見聞きしたりするものの、私たちにとってリアルに感じにくいのも事実。ですが、消費する社会に懸念して生まれたサステナビリティは、実は私たちが日常でよく飲むコーヒーにも必要な事として共有されています。
都会にはない沖縄の自然が溢れる場所で、想像だけでしか知らなかったコーヒーノキとチェリーたち。生産国の環境よりも随分と易しいものとわかっていても、自分の手で摘んだチェリーをコーヒー豆に精製していくことは、少しでもこの世界が持つリアルに近づける経験でした。
私たちが何気なく飲んでいるものは、雄大な自然とそこに営む人々の努力によってもたらされていて、これから先もずっと続くことはとても大変なことかもしれないと体感するきっかけにもなりました。今回の記事の内容は摘み取ったチェリーをコーヒー豆に精製していく過程になっています。コーヒーチェリーを摘んだワークショップの最初の記事は以下のリンクからどうぞ。
日本でも体験できるコーヒーの収穫と精製。

又吉コーヒー園併設のコテージからの風景。南国ならではの青空と木々たちを五感で味わいながら、コーヒー豆の収穫・精製・焙煎のワークショップを受けてきました。
前回、収穫したコーヒーチェリーの精製をします。


約一時間かけて収穫したコーヒーチェリーたち。(写真は二人分です)ワークショップでは、プラスチックカップ一つに満杯のチェリーを収穫しました。この量がだいたいコーヒー一杯分の量になります。
コーヒーチェリーの果肉を除去する工程


又吉さんの説明を聞きながら、コーヒーチェリーの果皮と果肉を手で取り除いていきます。


摘んでプチッと押し出していきます。


個人的なイメージとしては、枝豆を食べるときみたいにプチプチと果肉の中のコーヒー豆を取り出していきました。
黙々とコーヒー豆を取り出しています。





プラスチックカップにたくさんあったチェリーも果肉を取り除いてコーヒー豆だけになると、たったこれだけになりました。普段、コーヒー豆を挽いて飲んでいる方には、想像より量が採れないと感じると思います。
取り出したコーヒー豆を水洗する工程。

コーヒーチェリーから種子(コーヒー豆)を取り出すと、とても甘いヌルヌルとした粘膜に覆われています。この粘膜を洗う工程を行っていきます。
手洗いしている様子


コーヒー豆をネットに入れて、水を張ったタライでジャブジャブして洗っていきます。


私たちが普段飲んでいる水洗式のコーヒーは、生産国のコーヒー農園などでは果肉を取り除いたあとに、きれいな水を張った発酵槽に漬け込む工程があります。コーヒー豆の味わいを引き出すのにとても重要な工程と聞きます。
今回は日帰りのワークショップですので発酵工程を省き、コーヒー豆を覆う粘膜質(ミューシレージ)を手洗いで取り除いています。
水洗いをしたコーヒー豆を乾燥させる工程へ



生産国などでは、水洗いをしたコーヒー豆はハンモックのような風通しの良いネットの上に広げられ、天日干しされます。今回のワークショップでは布でさっと水気を拭き取り、ガスコンロの熱風で乾かす方法でした。
乾燥には手網も使って。

拭き取ったあとは、手網焙煎にも使われる道具に入れてガスコンロの熱風で乾燥させていきました。




一見すると、手網焙煎をしているような風景。火に近づけすぎると焙煎前に加熱してしまうため、ガスコンロとの距離に気を使いながら乾燥させていきました。
本来なら水洗後の乾燥もコーヒー農園では数日かけています。発酵槽に漬けて水洗い、それから数日かけての乾燥工程と、チェリーを摘んでからの手間はまだまだありました。また、コーヒー豆の品質は精製過程の良し悪しに大きく影響があり、生産者の特徴や技術がこの工程に大きく反映されるようです。
焙煎をして完成したコーヒーの試飲は次回。

今回、コップ一杯に収穫したチェリーを精製して残った量はこれだけ。
コーヒーノキ一本から採れるコーヒーチェリーはおおよそ三キログラムと言われています。そこから生豆になると五百グラム、焙煎をすると四百グラムにまで減っていきます。そして今回の写真にある精製したコーヒー生豆は、これで約十グラムです。
一本の木からコーヒーは約四十杯しか作れません。そして、コーヒーノキが収穫できるようになるまでは約三年〜五年かかるそうです。また、とあるコーヒーショップによると五十年後にはコーヒーの収穫量は現在の四十%にまで落ちるとの情報も。
コーヒーノキの育成や収穫は時間と手間(人の労力)、緑豊かな自然環境も必要です。
サステナビリティはコーヒーだけの問題ではなく、生産者の働く環境から農業全体まで、世界全体の環境問題も含まれます。私たちが普段、何気なく飲むコーヒーはどこからどうやって来るのか知ることは、環境を持続させる事の大切さを改めさせ、それが世界を良くするきっかけの一つにもなると思っています。
一杯のコーヒーはとても貴重で、その一杯のコーヒーを何気なく飲める私たちは、とても幸運なこと。
ワークショップのコーヒーチェリー収穫の様子はこちら。
【コーヒーを知る旅】「又吉コーヒー園」沖縄産コーヒーの収穫・精製・焙煎ワークショップ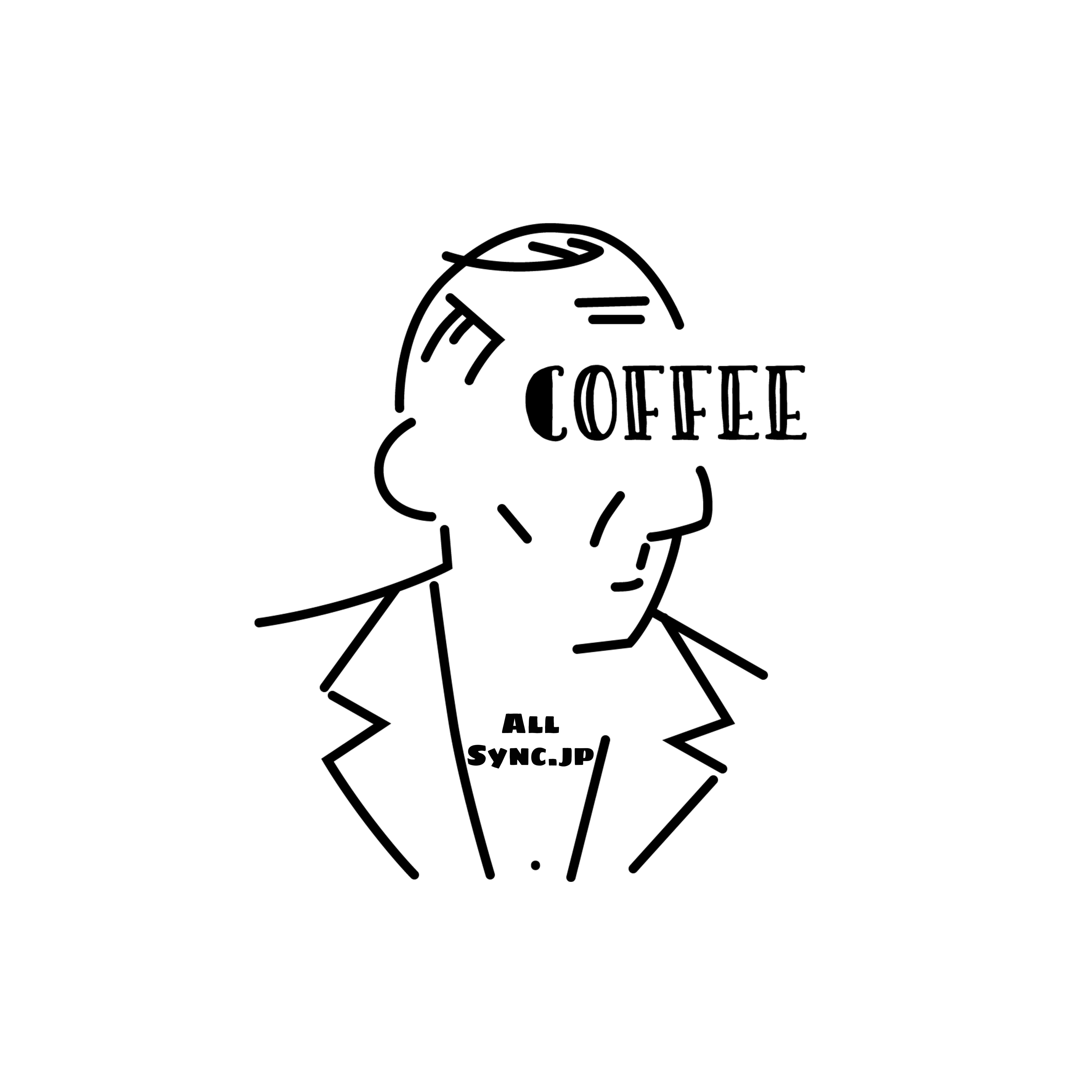
コーヒーは世界を良くする飲み物でもある。


